
データ統合とは?目的や進め方、データ統合基盤に必要なツールと事例を解説
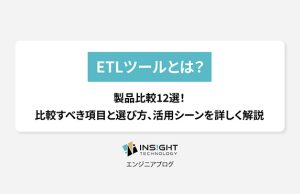
ETLツールとは?製品比較12選!比較すべき項目と選び方、活用シーンを詳しく解説
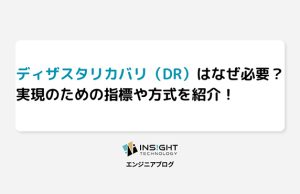
ディザスタリカバリ(DR)はなぜ必要?実現のための指標や方式を紹介
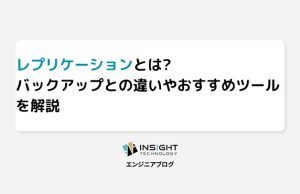
レプリケーションとは?バックアップとの違いやおすすめツールを解説
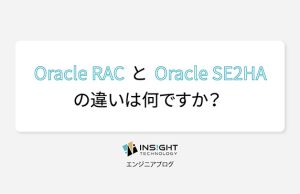
Oracle RACとOracle SE2HAの違いは何ですか?

すべてのSQL Server DBAがDbvisit Standby MultiPlatformを検討すべき5つの理由
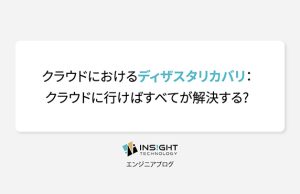
クラウドにおけるディザスタリカバリ:クラウドに行けばすべてが解決する?

straceで眺めるPostgreSQL

Amazon Redshift への移行に Insight Database Testing を活用する

改正個人情報保護法とデータベースセキュリティ(後編)

改正個人情報保護法とデータベースセキュリティ(前編)


